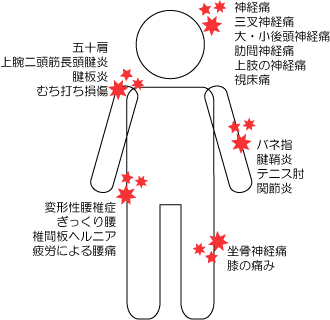はり・きゅうについて
鍼灸治療は個人個人の“証”(体質のようなもの)をもとに治療方針を決定するため、特別に強い症状がなくても、健康増進や、疲労の回復、病気の予防などを目的として治療を受けるということが可能です。
はり・きゅうの歴史
日本の鍼灸の源は中国医学にあります。
現存する最古の中国医学書などに記されている学術には、古代中国の自然哲学「陰陽」、「虚実」、「気・血・水」、「五行」などの考え方で整理されているために、現代医学の理論とは異なったものとなります。
日本で鍼灸が普及し独自の発展をしたのは江戸時代から明治初年にかけてです。それ以後は西洋医学を取り入れた医療制度に変わったため表舞台から遠のきました。
しかし、1970年代初め中国の鍼麻酔が話題になり、鍼の臨床効果が注目されるようになりました。それからと言うもの、はりやきゅうの科学的研究解明が進められた結果、確かな効果が証明され、医療技術のひとつとして普及するようになりました。
はり・きゅうが良く効く症状
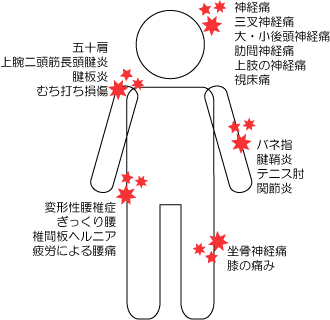
自律神経失調症・更年期障害
顔や手足のほてり、手足の冷え、肩こり、食欲不振、動悸、不眠、頭痛、吐き気、気がもめる、気力が出ない…などの症状。
麻痺
脳梗塞、脳出血の後遺症、末梢性顔面神経麻痺(ベル麻痺等)
内科系
胃弱、肝機能障害、便秘、下痢、高血圧、糖尿病、浮腫、脳貧血
小児科、婦人科系疾患
逆子矯正のお灸、妊娠腎、不妊症、生理不順、夜泣き.疳の虫、夜驚症、夜尿症、小児喘息、風邪予防、体調管理。
WiiやDSなどゲームによる仮性近視には、軽い皮膚刺激を主体とした小児鍼がおすすめ。
「痛み」を伴う疾患だけではありません!
医療の専門化、細分化が進んだ現代において、鍼灸施術の役割は「腰痛」「膝痛」「神経痛」など、主に『“痛み”に対する治療』を担当することが主になってきています。痛みの研究が進むにつれて、筋肉などの軟部組織に由来する症状の治療において、鍼灸施術が非常に有効かつ安全であることがわかってきたからです。痛みやしびれを感じさせている部位に鍼灸施術を行うことにより症状を緩和させることができます。
しかし、鍼灸施術の魅力は痛みを伴う疾患に対して効果的であるだけでなく、同時に自律神経の失調や、ホルモン系の不調による疾患にも大きな効果が期待できるところにあります。これは、人体の反射を利用した調整方法と考えられており、健康増進のためにも有効であるといえます。
また、今後は予防医学が重要になってくると考えられていますが、2000年以上前の中国の「黄帝内径」という古典の鍼灸医書に『未病を治するは名医なり』とも書かれています。当時からすでに、鍼灸は予防に重点を置いた治療を行っていたことがわかります。西洋医学では病名が決まってから治療が始まりますが、鍼灸治療は個人個人の“証”(体質のようなもの)をもとに治療方針を決定するため、特別に強い症状がなくても、健康増進や、疲労の回復、病気の予防などを目的として治療を受けるということも可能です。定期的に鍼灸施術を受療することで『病気になりにくい身体作り』ができるはずです。